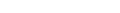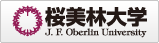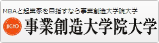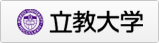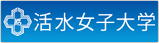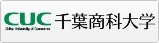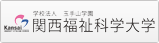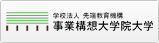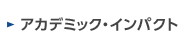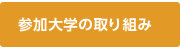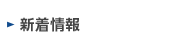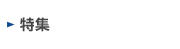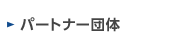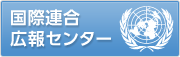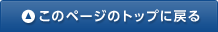2017.10.25
難民映画祭作品「シリアに生まれて」を本学で上映 ― 国連UNHCR協会の滝澤三郎理事長が講演

第12回国連UNHCR難民映画祭の作品の一つである「シリアに生まれて」の上映会を10月9日(月・祝)と20日(金)、本学中央教育棟で開催し、学生・一般の方など合わせて約700名が参加しました。
国連UNHCR難民映画祭は、映画を通して難民への理解を広げることを目的に大学をはじめ教育機関とも学校パートナーズとして提携し、啓発活動を展開しています。UNHCRと連携協定を結ぶ本学では、今回初めて学校パートナーズに参加。開催にあたっては、国連の平和運動を推進する本学学生団体ASPIRE SOKAとの共催で準備にあたりました。
上映前に、国連の平和運動を推進する本学学生団体ASPIRE SOKAの古賀広之さん(教育学部4年)が「本日の映画鑑賞を通して、一人でも多くの方に自分にできる一歩を踏み出してほしいと思います」と開催意義を述べました。また、経済学部4年の田口敏広さんが、難民キャンプを訪問して現地の人たちと触れ合った様子を報告し、平和のために貢献できる力をつけたいと発表しました。
田代康則理事長の挨拶の後、国連UNHCR協会の滝澤三郎理事長が「難民問題とUNHCR:日本の果たす役割」と題して講演。世界で増え続けるシリアなどの難民と国内避難難民の過酷な現状を伝えるとともに、「自分にできることは何かを問い続け、今回の映画祭を機に、紛争や貧困、難民問題に向きあい続けてほしいと思います」と学生たちに語りかけました。
上映作品「シリアに生まれて」は、いまだ戦闘が絶えないシリアを逃れ、難民となった子どもたちの現実を描いており、爆撃により負傷し、家族と生き別れ、子どもとしての時間を奪われ、それでも新たな希望を胸に逞しく生きる7つの小さな命にカメラが寄り添うドキュメンタリーです。鑑賞した方からは次のような声が寄せられました。
- これまで「難民」と聞いてもあまり興味がわかず、自分とは関係のない問題と思っていました。本日の講演と上映会を通して、「難民」は決して他人事ではなく、身近な問題として考えていく必要があると意識が変わりました。(20代、学生)
- シリア内戦が思っている以上に皮肉で残酷なものであることを目の当たりにしました。弱者を受け入れられないこの世界に憤りを感じました。まずは自分にできることから行動にうつしていこうと思います。(50代、主婦)
- 難民問題の過酷な状況を初めて知ることができました。戦争や紛争の軍事的な問題の解決も重要ですが、それによって引き起こされる難民問題は緊急の課題であると痛感しました。(40代、主婦)
- 難民問題は身近のことであると感じました。自分が不自由に感じていることが、他の人にとっては贅沢や自由であるとわかりました。学べる環境にあることに感謝し、困っている人の役に立てるよう学び続けていきます。(10代、学生)

第二回講演には約400名が参加

国連UNHCR協会の滝澤理事長の講演

中央教育棟エントランスではパネル展示を開催
最近の記事
-
2024.07.01
7月10日:創価大学「ポストスーパーグローバル大学創成支援キックオフ・シンポジウム」を開催― 国際NGO「核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)」事務局長が基調講演― -
2021.12.27
ユネスコスクール推進フォーラムを開催しました -
2021.12.01
ユネスコスクール推進フォーラム開催のお知らせ -
2021.11.17
映画「イージー・レッスン」の上映会を開催しました~WELgee代表の渡部カンコロンゴ清花さんが講演 -
2021.11.15
12/4「『世界市民』としてSDGsの時代を生きる」をテーマに、朝日教育会議2021フォーラムを開催します