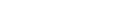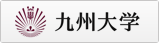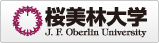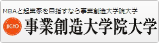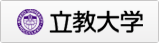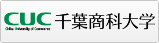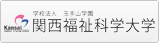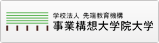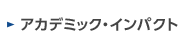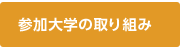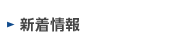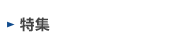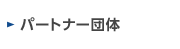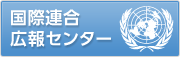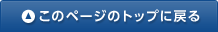2022.11.17
東京都立大学大学院都市環境科学研究科の大澤剛士准教授が研究発表「農地が持つ洪水発生の抑制機能は流域全体に及ぶ 〜流域治水の実現に貢献〜」を公開しました。
1.概要
気候変動の影響等によって甚大化する水災害に対応するために、河川域にとどまらず、集水域(雨水が河川に流入する地域)から氾濫域(河川等の氾濫により浸水が想定される地域)を含めて一つの流域と捉え、流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策に取り組む「流域治水」という考え方が広がりつつあります。これを実現するための一つの要素として、農林水産省が提示する「農業・農村の有する多面的機能」にも含まれる、農地が持つ防災・減災機能への期待が高まっています。
東京都立大学大学院 都市環境科学研究科の大澤剛士准教授は、東京都と神奈川県を中心とした関東地域における複数の流域および市町村を単位に、洪水被害の発生頻度と土地利用の関係を検討し、特定立地に存在する農地は水田、乾燥畑といった形態に関わらず、洪水の発生抑制に貢献している可能性を示しました。さらに簡単な数値シミュレーションを実施することにより、農地が持つ洪水の発生抑制効果は、流域を単位にすることで、より高くなる可能性を示しました。このことは、同一流域内においては、中山間地等、都市域から遠く離れた場所に立地する農地であっても市街地における水災害の発生抑制に貢献していることを示唆しており、水災害に強い土地利用を考える上で重要な指針になります。
2.ポイント
- 流域治水は、気候変動等に伴って近年増加する水災害に対抗するためのアイディアです。
- 水が溜まりやすい場所に立地する農地は、水田、乾燥畑といった利用形態に関わらず、洪水発生を抑制する機能を持つことが示唆されました。
- さらに、農地が持つ洪水抑制機能は流域全体に及び、同一流域内においては、市街地から遠く離れた農地であっても、市街地における水災害の発生を抑制できる可能性が示唆されました。
- 本研究の結果は、農地が持つ防災・減災機能を発揮させるためには、市町村の壁を越え、流域を単位とした土地利用計画を行うことが必要であることを示唆します。
3.研究の意義と波及効果
「流域治水」は、流域内のあらゆる関係者が協働して水災害対策に取り組むものです。同一流域内に居住する関係者の中には、直接的な被害を受けやすい河川域の近くに居住している方や、河川から離れており、河川氾濫の危険性が低い地域に居住している方も含まれます。しかし、本研究の結果は、水害が発生した地域から遠く離れた場所の農地であっても防災に貢献することを示唆しています。流域を単位として水害を考える場合、受益者と負担者が一致しないことはしばしば議論されますが、どのように負担を配分するべきかという指針は限られています。本研究の成果は、将来の土地利用計画に向けた指針になると同時に、防災対策における負担配分を議論する上での基礎的な知見につながることが期待されます。
——―
詳細は以下のWebサイトからご覧ください。
最近の記事