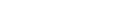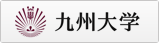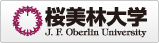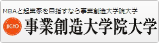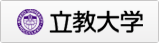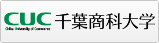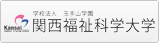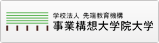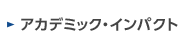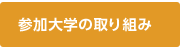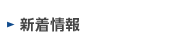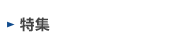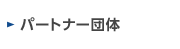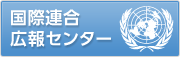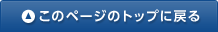2023.02.21
東京都立大学大学院都市環境科学研究科の三浦大樹准教授らが研究発表「炭素資源循環を革新する新しい触媒反応技術を開発 ~バイオマスや廃プラスチックからの高機能化成品製造に期待~」を公開しました。
1.概要
2050年カーボンニュートラル実現のために、再生可能資源や廃棄物などの有効利用を可能にする新しい技術が求められています。再生可能な炭素資源である木質バイオマスや、ポリエチレンテレフタレート(PET)に代表されるポリエステルなどには、多くの炭素―酸素結合(C–O結合)が含まれており、それらを効率的に変換できる化学反応は非常に重要です。これまではC–O結合を炭素―水素結合(C–H結合)に変換することで付加価値の低い炭化水素へと誘導する触媒系が多く、より直接的に有用化成品へと誘導できる新しい結合変換技術の開発が強く望まれていました。
東京都立大学大学院 都市環境科学研究科の三浦大樹准教授、土井雅文(大学院生)、安井祐希(大学院生)、正木洋佑(修士課程修了)、西尾英倫(大学院生)、宍戸哲也教授らは、C–O結合を炭素―ケイ素結合(C–Si結合)に効率的に変換し、有機無機ハイブリッド材料や医薬品などの原料として非常に有用な有機ケイ素化合物を効率よく合成できる新しい触媒反応の開発に成功しました。今回開発した技術は、木質バイオマス由来化合物から有機ケイ素化合物などの有用化成品を効率よく合成できるだけでなく、従来、炭素資源として利用されていなかったポリエステルなどを原料とすることも可能にしました。本技術により、新しい資源循環経路の提案や、カーボンニュートラルの実現が期待されます。
本研究成果は、2月20日付(アメリカ東部時間)でアメリカ化学会が発行する英文誌『Journal of the American Chemical Society』にて発表されました。また、本研究は創発的研究支援事業 FOREST(JPMJFR203V)および日本学術振興会 科学研究費助成事業(JP17H06443、JP21H01719、JP22K18927)の支援のもとで行われたものです。
2.ポイント
- 安定なC–O結合をC–Si結合に直接変換することが可能な担持金ナノ粒子触媒の開発に成功した。
- バイオマス由来の有機化合物を付加価値の高い有機ケイ素化合物へと効率よく変換できる。
- ポリエステル中のC–O結合もC–Si結合へと変換でき、廃プラスチック資源化への応用が期待される。
- 担持金ナノ粒子触媒は繰り返し利用することが可能であり、低コストで高付加価値化成品を製造することが可能である。
3.研究の意義と波及効果
本研究で開発した触媒反応技術を活用することで、木材などの再生可能な炭素資源から有機無機ハイブリッド材料や医薬品の中間体など高い付加価値を有する化学品を大量かつ迅速に製造するプロセスの実現が期待できます。さらに、ポリエステルなどを原料にして有用化成品を製造することが可能であるため、プラスチックごみ問題の解決に貢献するだけでなく、これまで用いられていなかった廃プラスチックなどを炭素資源とする新しい資源循環経路の提案や、カーボンニュートラルの実現が期待されます。
——―
詳細は以下のWebサイトからご覧ください。
https://www.tmu.ac.jp/news/topics/35447.html
最近の記事
-
2026.01.09
「人と共存するためのロボットのためのシステム統合」MS-CcS-L5G-serBOTinQセミナー & 研究討論の開催 -
2026.01.09
子ども・若者貧困研究センターでは、2025年『子どもの貧困研究のフロンティア定例学術研究会』を開催しました。 -
2026.01.09
水素エネルギー社会構築推進研究センターが『2025年度水素エネルギー社会構築推進研究センター講演会』を開催しました。 -
2025.07.02
ダイバーシティ推進室ニュースレター 第40号を発行しました -
2025.07.02
子ども・若者貧困研究センターが2025年『子どもの貧困研究のフロンティア定例学術研究会』(第48回)を開催しました。