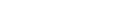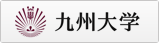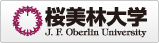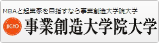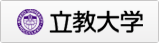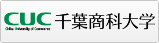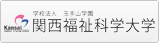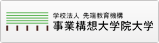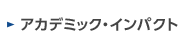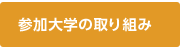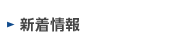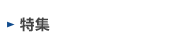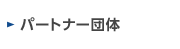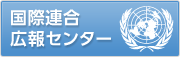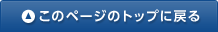2022.05.11
東京都立大学大学院理学研究科の山添誠司教授らが研究発表「既存技術を凌駕!世界最速級!空気中のCO2高速回収技術の開発」を公開しました。
1.概要
現在、気候変動問題を解決するため、二酸化炭素の回収、利用技術の確立が急務となっています。しかし、既存の大気中の低濃度二酸化炭素(400ppm)を回収する技術(Direct air capture, DAC)では効率・コストの面で改善の余地があり、新しいDAC技術の開発が望まれています。
東京都立大学大学院理学研究科の山添誠司教授、藤木裕宇(大学院生)、天本和志(大学院生)、吉川聡一助教、京都大学触媒・電池元素戦略拠点の平山純特定助教、東京都立大学大学院都市環境科学研究科の三浦大樹准教授、加藤玄(大学院生)、宍戸哲也教授らは、相分離を利用することで二酸化炭素吸収速度の向上と反応系からの生成物の分離を実現し、ガス流通下でも400ppmの二酸化炭素を99%以上の効率で除去する新しいDACシステムの開発に成功しました。
今回の研究では、シクロヘキシルアミン基をもつジアミン化合物の一種であるイソホロンジアミンが二酸化炭素と反応すると、不安定なカルバミン酸が固体として得られることを利用して、大気中の低濃度二酸化炭素を高速で吸収できるDAC技術の開発に成功しました。固体のカルバミン酸が懸濁した水溶液を60℃に加熱すると吸収した二酸化炭素を全て放出・回収できること、イソホロンジアミン水溶液は繰り返し利用可能であること、他のアミンでも本システムを適用可能であること、既存技術と比べ二酸化炭素吸収速度が2倍以上速いことから、今回、発見した相分離を利用した二酸化炭素吸収・回収システムは新しいDACシステムとして実用化が期待されます。
2.ポイント
- 液体のアミンと二酸化炭素が反応してできるカルバミン酸が固体として“相分離”することで、大気中の低濃度二酸化炭素(400ppm)と99%以上の効率で吸収できる新しいDACシステムを開発しました。
- 固体のカルバミン酸が懸濁した水溶液を60℃程度に加熱すると吸収した二酸化炭素を脱離・回収できることを見出しました。
- 本システムは400ppm~30%と幅広い濃度の二酸化炭素を99%以上の除去効率で吸収できること、固体のカルバミン酸を生成するアミンであれば適用可能であることから、今回開発した相分離による二酸化炭素吸収・回収システムは、DACだけでなく工場の排気ガス等からの二酸化炭素回収にも応用可能な汎用性の高いシステムです。
3.研究の意義と波及効果
本研究で開発した相分離によるDACシステムは、水溶媒中でも機能すること、DACシステムにおいて世界最速の二酸化炭素除去効率を示すこと、吸着材に用いているイソホロンジアミンの利用効率が高いこと(ジアミン1分子あたり二酸化炭素1分子が反応)から、既存の技術を超える高効率のDACシステムとなることが期待されます。また、60℃に加熱するだけで吸収した二酸化炭素を脱離・回収することができるだけでなく、吸収材は繰り返し利用可能であることから、低コストでの二酸化炭素回収も可能です。さらに、本研究では、実際の空気中の二酸化炭素を長時間除去できることも実証しているため、システムの大型化と更なる低コスト化を達成することで、これまでのシステムを凌駕する新しい相分離DACプラントを実現できると考えています。現在、我々の研究グループではNEDOプロジェクト「未踏チャレンジ2050」でDACシステムだけでなく、バイオマス由来の化合物を用いた二酸化炭素変換反応の開発も進めています。本研究で開発した相分離を利用したDACシステムと二酸化炭素変換反応システムを組み合わせることで、空気からプラスチックや化成品を作り出す“ビヨンド・ゼロ”の社会を実現できると考えています。
——―
詳細は以下のWebサイトからご覧ください。
最近の記事