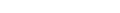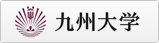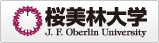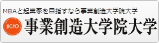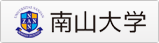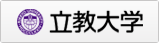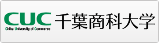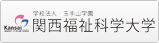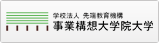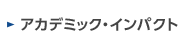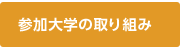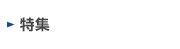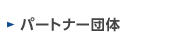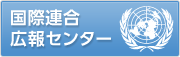本研究のポイント
- 光照射によって働く試料とプローブ間の力(光圧( 解説1))を計測する「光誘起力顕微鏡( 解説2)」で、高性能な光触媒(解説3)機能を持つナノ微粒子の近接場光(解説4)を画像化することに成功
- 照射光による熱の影響を独自技術で排除し、世界で初めて1ナノメートル以下の分解能(解説5)を達成。光圧の3次元ベクトルの画像化にも初めて成功
- 機能性ナノ材料の設計・評価のための新しい基盤技術として期待
研究概要
石原 一 教授(大阪府立大学工学研究科/大阪大学大学院基礎工学研究科)、菅原 康弘 教授(大阪大学大学院工学研究科)、鳥本 司 教授(名古屋大学工学研究科)らの研究チームは、光照射により発生する力(光圧)を計る顕微鏡(光誘起力顕微鏡)を用いて、人工合成されたナノ粒子の近接場光を1ナノメートル(10億分の1メートル)以下の分解能で画像化することに世界で初めて成功しました(図1〜3)。
半導体や金属のナノ粒子は光触媒、太陽電池などに用いる光機能材料として注目されています。光を用いる走査型顕微鏡(走査型近接場光学顕微鏡( 解説6))は、このような試料の光学特性を反映した画像が得られる利点がありますが、原子スケールの分解能までは得られませんでした。今回、光を照射した走査型顕微鏡のプローブ先端とナノ材料の間に働く力(光圧)を高感度に読み取る新しいタイプの顕微鏡(光誘起力顕微鏡)により、桁違いの高分解能を実現することができました。
研究チームは高性能な光触媒材料として設計された複合ナノ粒子を複数の波長の光を用いて観測し、ナノ粒子が設計通りの化学的性質を持つことを原子分解能に迫る光圧画像で確認しました。超高真空中での観測を実現し、かつ光照射による熱の影響を除去する独自の工夫を加えたことが高分解能の鍵となり、光圧の3次元ベクトル像を取得することにも成功しました(図4)。機能性ナノ材料の設計・評価のための新しい基盤技術として期待される成果です。
詳細は以下のWebサイトからご覧ください。